終活コラム
vol.42
お坊さんは一日、何しているの?
葬儀や法要の時にお世話になる「お坊さん」 皆さんは、どういった印象をお持ちですか? 「話しかけづらい」「無口な印象」など、様々かと思います。 今回は遠い存在に感じる「お坊さん」について、色々ご紹介しますね。
お坊さんの一日
よくお坊さんの朝は早いと聞きますが、お坊さんは、いつも何しているのでしょうか?
朝5~6時前
起床。身支度をして寺の門を開け、境内を掃除します。
↓
朝7時前
朝の勤行(ごんぎょう)を行います。
勤行とは仏前でお経を読んだり礼拝することをいい、「お勤め」とも言われています。
↓
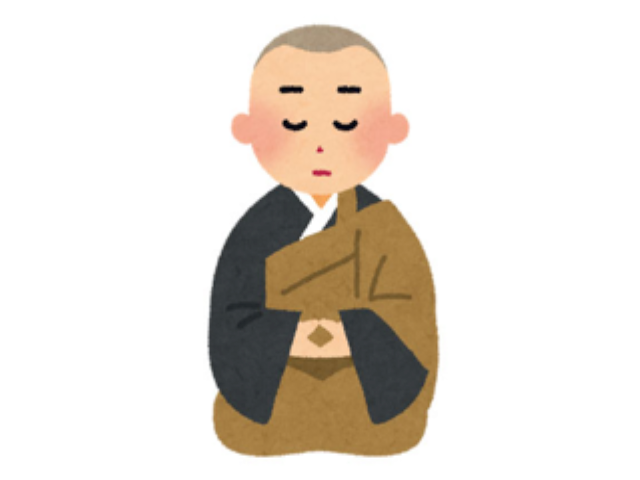 朝9時頃
勤行が終わると朝食になります。
自分のお寺であれば、一般家庭と変わらない朝食ですが、修行寺の場合、肉類のない「精進料理」になります。
↓
朝食後
お葬式や法要などが入っているかどうかで変わってきます。
仮にお葬式が入っている場合、告別式で読経し出棺、火葬まで立ち会い読経を行います。その後、遺族の人達と食事を一緒にします。
また他に葬儀、通夜などが入っていれば移動します。通夜の場合は、最後の参列者が帰えるまでいなければいけないので、帰宅は21時前位になるそうです。
また何もない日は、檀家の方へお知らせを送るなど事務仕事などをします。
16時位から夕方の勤行を行い夕食になります。
また帰宅が遅い場合も「勤行」をやらないといけないのです。
疲れて帰ってきてもこの「お勤め」は、さぼってはいけないのです・・。
↓
お勤めが終了後
翌日に備えて22時位には寝るそうです。
朝9時頃
勤行が終わると朝食になります。
自分のお寺であれば、一般家庭と変わらない朝食ですが、修行寺の場合、肉類のない「精進料理」になります。
↓
朝食後
お葬式や法要などが入っているかどうかで変わってきます。
仮にお葬式が入っている場合、告別式で読経し出棺、火葬まで立ち会い読経を行います。その後、遺族の人達と食事を一緒にします。
また他に葬儀、通夜などが入っていれば移動します。通夜の場合は、最後の参列者が帰えるまでいなければいけないので、帰宅は21時前位になるそうです。
また何もない日は、檀家の方へお知らせを送るなど事務仕事などをします。
16時位から夕方の勤行を行い夕食になります。
また帰宅が遅い場合も「勤行」をやらないといけないのです。
疲れて帰ってきてもこの「お勤め」は、さぼってはいけないのです・・。
↓
お勤めが終了後
翌日に備えて22時位には寝るそうです。
お坊さんの繁忙期はいつ?
お坊さんの繁忙期といえば・・「春秋のお彼岸」と「夏のお盆」です。 地方によっては、お坊さんが檀家を一軒一軒まわって読経を行うという風習があるため、休む暇がないほど、お坊さんにとって忙しい時期でもあり、遠方にいる檀家さんとも交流出来る大切な時期でもあります。 お寺によって様々ですが、過去帳というものがあるお寺もあります。 過去帳とは檀家の中で、亡くなった人の法名・命日・俗名・喪主など全てを記録したものがあります。この過去帳をチェックしていつ法要があるか確認し、檀家の方と日程を調整します。 檀家の方との関わり以外にも、ほぼ毎月仏教の行事に参加しなくてはいけません。
仏教の年中行事
1月 修正会(しゅうしょうえ)
正月の初めに、お寺では社会の平和と人々の幸福を祈って、法会(ほうえ)という仏教において仏法を説くためや供養を行うために僧侶達が集まる行事です。
2月 涅槃会(ねはんえ)
2月15日は、お釈迦様の亡くなった日です。
仏教寺院では毎年、お釈迦様の入滅の日に法要を行います。
 3月 春彼岸会
4月 花祭り(灌仏会「かんぶつえ」)
お釈迦様の誕生を4月8日にお祝いする行事です。
7月 四万六千日(しまんろくせんにち)
7月10日に行われる縁日で、この日に参詣すると、四万六千日参詣したほどの功徳(くどく)があるといわれています。
8月 孟蘭盆会(お盆)
9月 秋彼岸
12月 成道会(じょうどうえ)
お釈迦様が悟りを開いた事を記念して12月8日に行う法要です。
「花祭り」「涅槃会」「成道会」は、「三大法会」として重んじられています。
3月 春彼岸会
4月 花祭り(灌仏会「かんぶつえ」)
お釈迦様の誕生を4月8日にお祝いする行事です。
7月 四万六千日(しまんろくせんにち)
7月10日に行われる縁日で、この日に参詣すると、四万六千日参詣したほどの功徳(くどく)があるといわれています。
8月 孟蘭盆会(お盆)
9月 秋彼岸
12月 成道会(じょうどうえ)
お釈迦様が悟りを開いた事を記念して12月8日に行う法要です。
「花祭り」「涅槃会」「成道会」は、「三大法会」として重んじられています。
年中無休の「お坊さん」
お坊さんは、実は「年中無休」なのです。 いつお葬式があるか分かりません。 檀家の方が亡くなった時に「出かけていて、葬式が出来ない」なんて事になったら一大事です。 お寺や宗派によって、1日の過ごし方も参加行事も様々かと思います。 しかしお坊さんは完全に1日休みという日はなく、多忙な日々を送っているのです。





